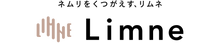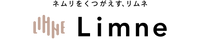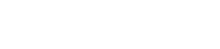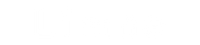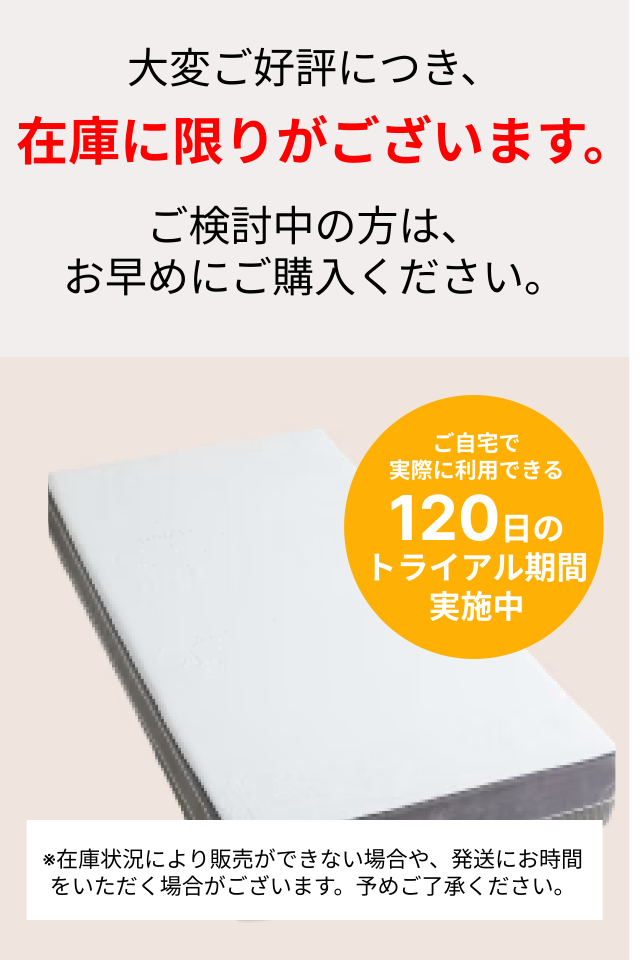〜寝る前の頭痛〜症状を抑えて快適な眠りを手に入れるには?
寝ようと思って布団に入ると頭痛がひどくなる、睡眠中に頭が痛くて目が覚めると悩んでいる方へ。
就寝前に頭痛がすると不眠で寝不足になるし、病気かもしれないと心配にもなりますよね。
実は、寝る前に起こる頭痛には種類があり、それぞれ原因も対処法も異なります。
間違った対処法では痛みを増幅させるなど、逆効果になります。まずは自分がどのタイプの頭痛なのかしっかりと把握し、それに合った対処を行うことが大切です。
頭痛から解放され、毎日快眠できるよう、ぜひチェックしてみてください。
寝る前に起こる頭痛は主に2種類

頭痛には、女性に多く見られる片頭痛や男性に多い群発頭痛など、原因や症状が異なる複数のタイプがあります。
ここでは一次性頭痛と言われる片頭痛と緊張型頭痛、それぞれの原因や特徴を紹介します。
どちらも繰り返し起こる頭痛(慢性頭痛)で、悩んでいる人が非常に多いです。
寝る前に起こる頭痛がどちらに当てはまるか、確認をしてみましょう。
片頭痛
1つ目は片頭痛です。
頭の片側だけでなく、ときには両側も痛み、就寝前だけでなく睡眠中や起床時に起こることもあります。
片頭痛には、唐突に起こる「前兆のないケース」と「前兆のあるケース」があります。前者の場合はキラキラした光が見えたり、視野の一部が見えにくくなったりすることがあります。
症状としては、こめかみから目のあたりがズキンズキンと脈打つような痛み(拍動性頭痛)がし、頭を動かすとより痛みが増してしまいます。ときには、吐き気や嘔吐などを伴うことも。
この片頭痛の原因は、脳にある視床下部が反応し、「セロトニン」という血管を収縮させる作用を持つ物質が放出され、脳の血管が急激に拡張することです。
その誘因は人によってさまざまですが、過眠や睡眠不足、ストレスによる自律神経の乱れ、女性ホルモンの量の変動、空腹、疲労、食品の種類、生活リズムの乱れ、雨天による気圧の変化など、多岐にわたります。
緊張型頭痛
2つ目は緊張型頭痛です。
症状としては、部分的ではなく、頭全体を締め付けられるような痛みが出ます。片頭痛と異なり、頭を動かしても痛みは増えません。
また、肩や首のこり、めまいを伴うことや、デスクワーク後に痛みが発症することもあります。
この緊張型頭痛の原因は、筋肉のこりや精神的なストレスによって血流不良が起き、それによって頭の周りや首、肩の筋肉が緊張することです。
寝る前の頭痛を予防する方法
寝る前に起こる2種類の頭痛の症状と原因を紹介しました。
では、それらの頭痛を予防する方法を見ていきましょう。
片頭痛の予防方法
片頭痛の原因の1つに、睡眠の質の低下が挙げられます。
疲れやストレス、普段の生活習慣の乱れが睡眠の質を下げ、寝不足を招きます。また、普段の睡眠不足を解消するために、週末に寝だめをするのもNGです。寝すぎも睡眠の質を下げるため、良くありません。
つまり、そういった睡眠の質の低下が片頭痛を招く原因になっているため、睡眠の質を改善することが予防に役立ちます。
では、どうすれば睡眠の質を上げることができるのでしょうか。
1つ目は、朝起きたらカーテンを開け、日光を浴びて体内時計をリセットすることです。体内時計は覚醒と睡眠を切り替えて、自然な眠りを誘う作用があります。
体内時計がリセットされてから14〜16時間後に睡眠ホルモンである「メラトニン」が分泌されるので、毎朝決まった時間に朝日を浴びると睡眠の習慣を作ることができます。
生活のリズムを整えることで、毎日のスムーズな入眠と質の良い眠りにつながるのです。
2つ目は、就寝環境を整えることです。眠気を促すホルモンであるメラトニンは、光の刺激で分泌が抑制されてしまいます。つまり、寝室が明るいと眠くなりにくいため、部屋の照明を調節する、あるいは間接照明で薄暗くするのがおすすめです。
また、自分の体に合った寝具を使うことも重要。いくら生活習慣や環境を変えても、寝具が合っていなければ睡眠の質を上げることはできません。

首に負担がかからないように枕の硬さや高さが合っているかを確認し、合っていないようであれば、クッション材を足したり、タオルを重ねたりして調節しましょう。
掛け布団は重すぎないものを選ぶのがポイント。重すぎると身体が押さえ付けられて寝返りが打ちにくく、夜中に目が覚めたり、朝起きたときに身体が痛くなっていたりすることがあります。通気性の良さも不可欠です。通気性の悪いものだと、汗をかいて目が覚めてしまうことがあります。
敷き布団やベッドのマットレスの硬さも重視しましょう。硬すぎると身体の曲線にフィットせず、快適に眠れなかったり、痛くなったりします。反対に柔らかすぎると身体が沈み込んで寝返りが打ちにくく、負担がかかります。そのため、適切な硬さのものを選ぶことが大切です。
【片頭痛を誘発しやすいとされる食品を避ける】
片頭痛は食事も関連しているので、誘発しやすい食品は避けるようにしましょう。

具体的には赤ワイン、チョコレート、チーズ、ハム、ヨーグルトなどです。これらの食品には、チラミンなどのアミン類という片頭痛誘発物質が含まれています。
普段の食事でこれらの食品を摂取しており、片頭痛の症状が起こっている人は、一旦摂取を控え、症状が改善するか確認してみましょう。
【頭痛の原因を特定する】
片頭痛の予防方法をご紹介しましたが、まずはその原因を特定するのが先決です。
何が原因か分からなければ対処の仕様がないので、次のように、頭痛が起きた日や起きなかった日、その状況までメモしておくといいでしょう。もしかすると、原因が見えてくるかもしれません。
- ここ最近、睡眠不足が続いている
- ワインを飲んだ日の夜だけ頭が痛くなった
- ホテルに泊まったとき(自分の寝具を使わなかったとき)には、頭痛が起きなかった
もし原因が分かれば、それを改善することで片頭痛を避けられるはずです。
緊張型頭痛の予防方法
ここでは、緊張型頭痛の予防方法について見ていきましょう。
【適切な高さの枕を使う】
緊張型頭痛の原因に、首や肩のこりによる血行不良があります。寝るときの枕が高すぎ、あるいは低すぎで合っていないものだと、首や肩に負担がかかり、血行不良を招いてしまいます。
枕の高さが合っていない場合は、自分に合ったものに買い直すか、タオルを下に敷いて、頭が適切な位置に来るように調整してください。
それによって睡眠時に首や首まわりの筋肉を休めることができ、緊張型頭痛を予防できます。
【日中、長時間同じ姿勢で作業しないよう心がける】
日中の姿勢も大事で、デスクワークで座りっぱなしなど、同じ姿勢を続けることで肩や首のこりを招いてしまいます。
そうすると血行不良を起こし、緊張型頭痛の原因になるので、椅子から立つ、前屈するなどの軽い運動を定期的に行うようにしましょう。
起きている間も寝ている間も、血行不良を招くような姿勢には注意が必要です。
 |
 |
寝る前に頭痛が起こった場合の対処法
では、実際に寝る前に頭痛が起こった場合の対処法をご紹介します。
片頭痛と緊張型頭痛とでは対処法が異なるので、自身の症状に合わせて行ってみてください。
片頭痛の対処法

片頭痛の原因は脳の血管が膨張することなので、痛む箇所を冷やすのが効果的です。
冷たいタオルやアイシングバッグなどを当てて、血管を収縮させると片頭痛を軽減させることができます。
また、逆に温める行為は血管が拡張して痛みが増すことにつながるため、NGです。片頭痛が出ているときは、マッサージや入浴など痛む箇所を温める行為はもちろん、運動やストレッチも血流の流れが良くなるので避けましょう。
【寝室を暗くして安静にする】
片頭痛の発作中は、まぶしい光や騒音に敏感になって痛みが増す可能性があるため、テレビやスマホは見ず、寝室の照明も暗くして安静にしましょう。
また、頭を動かすと痛みが増すので、何もせずに横になってリラックスするのがおすすめです。
【鎮痛薬を服用する】
なかなか痛みが治まらない場合は、市販の鎮痛薬を服用しても良いでしょう。
鎮痛薬のなかには痛みや熱のもととなるプロスタグランジンの産生を抑え、頭痛を緩和する成分が含まれているので有効です。
それでも頭痛が続く場合は、ほかの病気が原因の可能性もあるため、専門医を受診しましょう。
緊張型頭痛の対処法

緊張型頭痛は片頭痛とは逆に、痛む箇所を温めるのが効果的です。
頭痛の原因が血行不良によるものなので、患部を温めることで血行が良くなり、痛みが緩和されます。
マッサージ、蒸しタオル、半身浴、ストレッチや軽い運動などで、血行の流れを良くしましょう。
【首や肩の筋肉をほぐす】
首や肩のこりによる血行不良の解消におすすめなのが、ストレッチです。
首がこっている場合は、左右に倒したり、ゆっくり回転させたりしてこりをほぐします。
肩がこっている場合は、両肩を耳に近づけるように両腕を上げて3秒キープした後、力を抜いて肩を下ろします。これを5~10回程度繰り返してください。両肩の筋肉をほぐれて、血行が良くなります。
【病院で診察を受ける】
紹介した予防法や痛みが出た場合の対処法を行っても症状がなかなか治らない、長引く場合は、別の病気の可能性があるため、医師に相談したほうがいいでしょう。
脳神経外科や脳神経内科の専門医でも、片頭痛の患者を三叉神経痛(さんさしんけいつう)や副鼻腔炎と誤診したりするケースもあるそうなので、頭痛外来があるような頭痛専門医を受診することをおすすめします。
寝る前に起こる頭痛の原因をはっきりさせ、予防と対処をしよう
寝る前に起こる頭痛には片頭痛と緊張型頭痛の2種類があること、それぞれに原因や対処法が異なることをご紹介しました。
まずは自分の症状がどちらの頭痛なのか見極め、それに合った対処を行うことが重要です。
もし、なかなか症状が改善されない、めまいや手足のしびれなどもある場合は、高血圧や脳腫瘍、くも膜下出血といった別の病気の可能性も考えられるため、医師に相談すべきです。
寝る前の頭痛は寝つきが悪くなるため、睡眠の質が下がり、日常生活にも支障をきたすので、しっかりと予防と対処をしていきましょう。
ただやわらかいだけじゃない。身体への負担も軽減する、まるでマシュマロの上で眠るようなマットレスです。